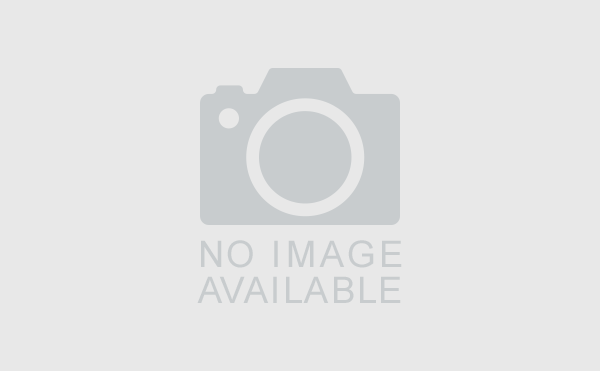【必見】雨の日の頭痛、だるさ、めまい…。天気の不調はなぜ起こる?東洋医学のプロが教える「天気痛」の根本原因とセルフケア法
【必見】雨の日の頭痛、だるさ、めまい…。天気の不調はなぜ起こる?東洋医学のプロが教える「天気痛」の根本原因とセルフケア法
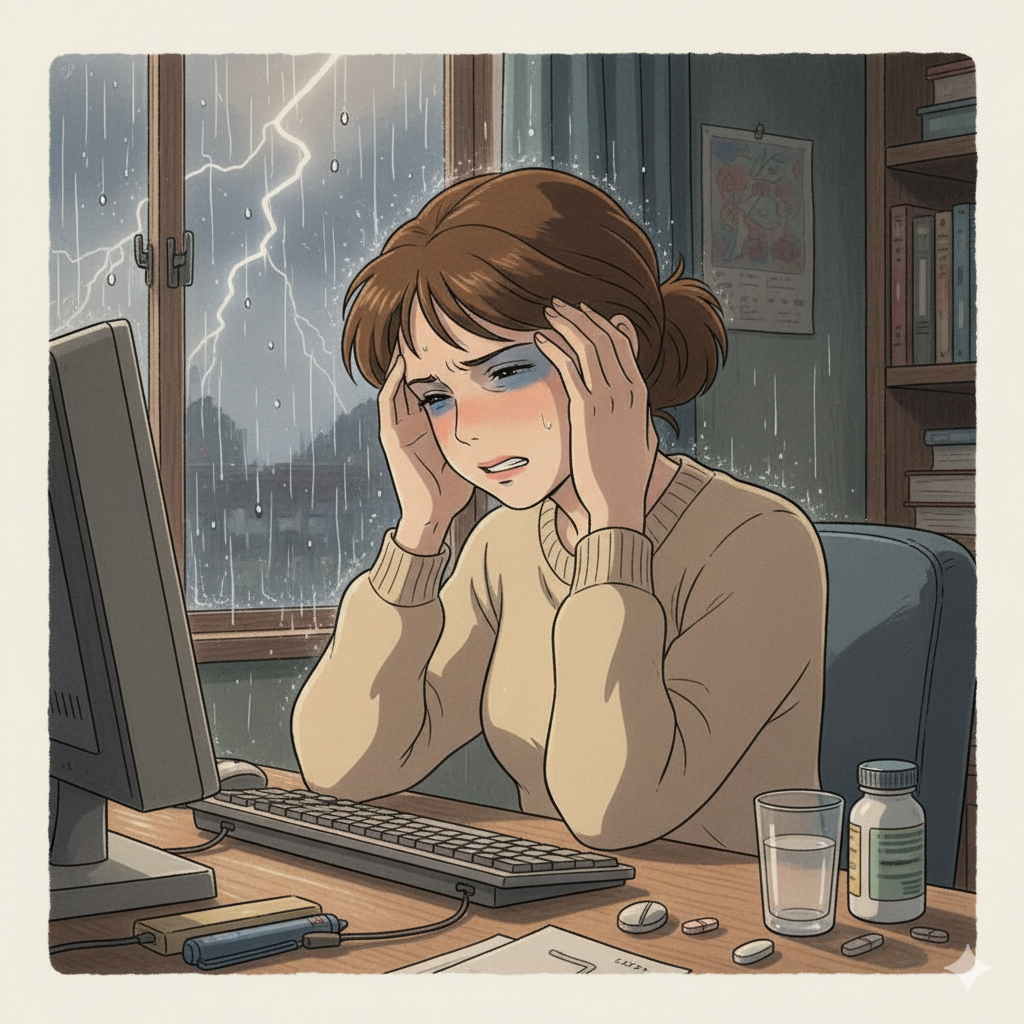
9月に入り、いよいよ台風シーズンがやってきましたね。
「天気が崩れると、決まって頭がズキズキする」 「体が重くて、どうしてもやる気が出ない」
当院でも、この時期になるとこうしたお声をたくさんいただきます。天気予報の雨マークを見るたびに、気分が憂鬱になる方もいらっしゃるかもしれません。雨が降ると考えただけで気が重くなったり、実際に体が重くなってしまったり…多くの方が経験していることだと思います。
実は、こうした雨の日特有の頭痛、めまい、むくみ、古傷の痛み、気分の落ち込みなどは、単なる気のせいや偶然ではありません。最近では、悪天候が体に不調を引き起こすメカニズムも少しずつ解明されてきました。
そして東洋医学では、はるか昔から天気が悪い時の不調を**「湿邪(しつじゃ)」**と呼び、様々な対処法を実践してきました。この記事では、その知恵を皆さまにご紹介していきたいと思います。
なぜ起こるの?東洋医学で考える「天気痛」の正体
キーワードは**「湿邪(しつじゃ)」**です。 これは、梅雨時期や夏の終わりなど、湿気が高い季節に起こりやすい体調不良の総称です。
そしてもう一つのキーワードが、体質を指す**「水滞(すいたい)」**という言葉です。 これは、体の「排水溝」が詰まり気味になっているようなイメージです。もともと体内の水分代謝が滞りやすいこの「水滞」体質の方が、外からの「湿邪」の影響を受けることで、天気痛の諸症状が引き起こされると考えられています。
体に余分な水分を溜め込んでいるため、寝起きがとても辛かったり、日頃から体が重だるく感じたり、疲れやすかったりするのです。
あなたはどのタイプ?「天気痛」になりやすい人の特徴
「湿邪」の影響を受けやすく、天気痛に悩まされやすい方は、以下のような特徴を持っていることが多いです。ご自身でチェックしてみましょう。
- □ 胃腸が弱く、おなかを壊しやすい
- □ 普段からむくみやすい(特に足や顔)
- □ 冷え性で、手足が冷たいことが多い
- □ 甘いものや乳製品、冷たい飲み物を好む
- □ 普段から肩こりや首こりがひどい
今日からできる!天気痛を和らげる3つのセルフケア養生法
1. 食事で「湿」を追い出す
まずは、体の余分な水分(湿)を追い出す働きのある食材を積極的に取り入れましょう。
- おすすめの食材: 小豆、とうもろこし、ハトムギ、海藻類
- おすすめの香味野菜: しそ、生姜、ねぎなど
2. ツボ押しで「水はけ」を良くする
「湿邪」に悩む方におすすめしたい、代表的なツボをご紹介します。
- 豊隆(ほうりゅう): 水分代謝を助ける代表的なツボ。
- 内関(ないかん): 自律神経を整え、めまいや吐き気を和らげる。
- 曲池(きょくち): 首や肩周りのこりにも効果的。
3. 生活習慣で「巡り」を良くする
- 軽い運動: ウォーキングやストレッチなどで、じんわり汗をかく習慣を。体内の水はけを良くするのに非常に効果的です。特に「第2の心臓」と呼ばれるふくらはぎを動かす運動は、全身の血流を健康的に循環させてくれます。
- 入浴: 夏場はシャワーだけで済ませがちですが、なるべくぬるめのお湯でも良いので湯船に浸かり、体を温めて発汗を促すことが重要です。(私も息子と入浴する際は脱水が怖くてシャワーが増えがちですが、親子共々しっかり温まる時間を大切にしています。)
- 「三首」を冷やさない: 外出すると暑い一方、室内は冷房が強いことが多いこの季節。「首」「手首」「足首」の三首が冷えると、体の巡りは一気に悪化します。薄手のカーディガンなどを一枚持ち歩き、体を冷えから守りましょう。
セルフケアでも改善しない…そんな時は鍼灸治療という選択肢
当院でも、天候による体調不良を訴える方は年々増えている印象です。日本の気候が温暖化の影響で、少しずつ熱帯的に変化する中で、患者さんのお悩みも変わってきているのかもしれません。
それに伴い、私たち鍼灸師の研究も進み、「天気痛にはこのツボが有効ではないか」といったアプローチも深まってきています。
もしあなたが、
- 今まで鍼灸を試したことがないけれど、長年の不調に悩んでいる
- 天気が悪い時だけ、決まってつらい症状が出る
- 薬だけに頼らず、根本的に体質を整えたい
そうお考えでしたら、ぜひ一度、鍼灸治療という選択肢を思い出してみてください。 天気に左右されない、軽やかな毎日を目指して、私たちが全力でサポートします。