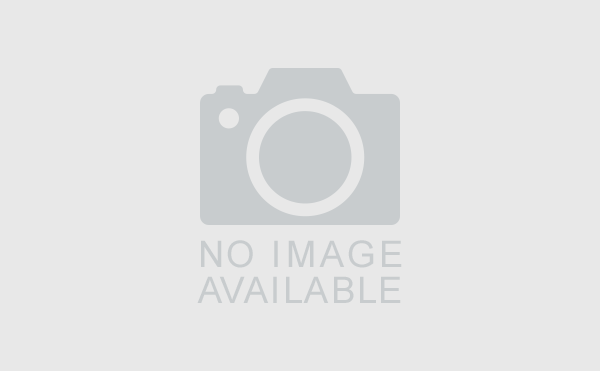今日から冬が始まります。「立冬(りっとう)」の養生法 ~東洋医学に学ぶ、エネルギーを「蓄える」冬の過ごし方~
こんにちは!横浜明堂鍼灸院の石尾です!
本日(11月6日)は、二十四節気(にじゅうしせっき)でいうところの「立冬(りっとう)」です。(※年によっては11月7日になります)
暦の上では、今日からいよいよ冬の訪れです。 日差しはまだポカポカと暖かく感じられることもありますが、朝晩の冷え込みは確実に増してきましたね。
私も最近、少しボーッとすることが多く、「季節の変わり目だな」と感じています。 このように、季節の変わり目に体調の変化を感じる方は一定数いらっしゃるかと思います。
東洋医学では、季節の変わり目は「体の使い方を変える」ための大切な合図と考えます。 いよいよ秋の「収穫」の季節が終わり、これからは「蔵(ぞう)=蓄える」季節の始まりです。
一緒に、この冬を元気に乗り越えるヒントを学んでいきましょう。
<b>なぜ冬は「蓄える」季節なの?</b>
熊が冬眠するように、本来、人間も冬は活動を(少し)制限し、エネルギーを消耗しないように過ごす方が良いとされています。 昔の書物にも「暑すぎる夏や寒すぎる冬は、働きすぎるな」という趣旨のことが書かれているほどです。
そして、東洋医学で冬に守るべき臓(ぞう)は「腎(じん)」です。 「腎」は、私たちの生命エネルギーの源を蓄えてくれている場所です。
この「腎」は寒さに最も弱いため、冬はしっかり「腎」を守ることが大切になってきます。
<b>「腎」を守らないと、どうなる?</b>
冬本番の寒さが来たとき、鍼灸院では首こりや肩こりの患者様がすごく増えます。お灸(きゅう)を使う場面や、痛みの訴えが増えるのもこの時期です。
体を冷やしてエネルギーを無駄遣いしてしまうと、この「腎」が冷えてしまい、
- 冷え性
- 腰痛
- とれない疲労感 といった「冬の不調」に直結してしまいます。
今のうちからしっかり「腎」を養い、冬の不調に備えていきましょう。
<b>冬におすすめの養生法 3選</b>
具体的に、冬の間におすすめする過ごし方を3つご紹介します。
<b>1. 睡眠:「早寝遅起(はやねおそおき)」</b>
これは「早く寝て、朝は(太陽が昇るまで)少しゆっくり起きる」という意味です。 昔は日照時間と活動時間が比例していました。電気というものができてからこれを守るのは難しくなりましたが、睡眠時間をいつもより少し伸ばすだけでも、体調が良くなるかもしれません。
<b>2. 防寒:「三首(さんくび)」を温める</b>
「三首」とは、「首」「手首」「足首」のことです。 これらの部分は皮膚が薄く、衣服からものぞきやすいため、冷えが入りやすい場所です。 ネックウォーマーやレッグウォーマーなどを活用し、場合によっては室内でもしっかり温めてあげましょう。
<b>3. 食事:「黒い食べ物」で「腎」を補う</b>
「腎」を守るには「黒い食べ物」がおすすめです。 (例:黒豆、黒米、黒ごま、ひじき、海苔、わかめ、きくらげ など)
また、根菜類(大根、にんじん、れんこんなど)も体を温めてくれるので、温かいスープなどで摂るのがおすすめです。
【まとめ】
「立冬」の期間(約2週間)を過ぎると、いよいよ本格的な冬のシーズンに入ってきます。
- しっかり体を温めて(特に三首!)
- いつもより、よく寝て
- 「腎」を補う黒い食べ物を摂る
これらを意識して、元気に冬を乗り越えましょう。
最近はインフルエンザなども増えています。喉をしっかり潤しておくことも予防につながりますね。(私は龍角散の飴が好きです)
冬の不調や寒さでお困りの方は、ぜひお気軽に「横浜明堂鍼灸院」までご相談ください。