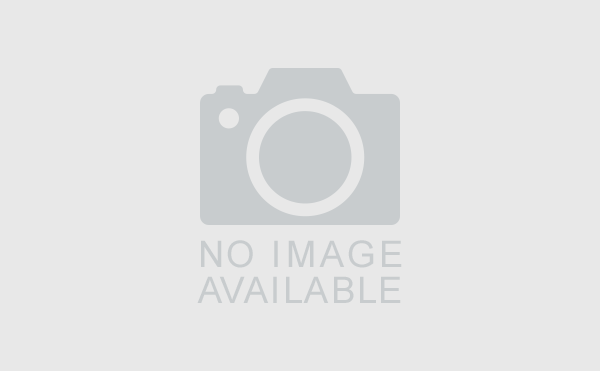その不調、「年齢のせい」と諦めてませんか?東洋医学の「腎(じん)」とアンチエイジングの深い関係
「立冬」を過ぎ、本格的な冬の入り口に差し掛かってきました。 東洋医学では、冬は「腎(じん)」の季節とされています。
「腎」と聞くと、腎臓疾患などを連想するかもしれませんが、東洋医学の「腎」はそれよりもはるかに広い、私たちの「エネルギー、命の源そのもの」を指しています。
(東洋医学では、意外なことに「脳」の機能というのをそこまで重要視していません。判断や決断といった部分は、脳ではない他の部分(例えば「肝」や「胆」)が担うと考えています。なぜ当時の中国人がこのように考えたのかは私も研究しているところですが、ともかく、「腎」の働きには「おしっこの濾過機能」だけでなく、非常に多くの意味が含まれているのです。)
例えば、「白髪が増える」「足腰が冷える」「疲れやすい」といったものが、その「腎」が弱っている状態、「腎虚(じんきょ)」の症状とされています。
冬に「腎虚」になってしまうのは、季節性のものもあります。 昔の東洋医学の知識を使って、少しでも「腎」を補う方法を、この記事でご紹介していきたいと思います。
もしかして「腎虚」かも?セルフチェックリスト
「腎虚」の症状には、「老化」とよく似た症状が多く含まれます。 こんなサインはありませんか?
- □ 慢性的な腰痛がある
- □ 足腰が冷えやすい、または力が出ない
- □ 疲れが抜けず、気力・体力が落ちたと感じる
- □ 白髪や抜け毛が増えた(「髪は腎の華」と言われます)
- □ 耳鳴りがする、または聴力が低下した(「腎は耳に開竅する」)
- □ 夜中に何度もトイレに起きてしまう
「腎」の症状と「老化」がいかに似ているか、よくご理解いただけるかと思います。
なぜ「冬」に「腎」を守るべきなのか?
冬は、「腎」が一年で最も弱まりやすい季節です。 だからこそ、この冬の間に「腎」をしっかり補い、体を温めながら過ごすことが、健康に冬を乗り越え、暖かい春を迎えるための「準備」になるのです。
鍼灸師が教える!冬の「腎」を養うセルフケア
「腎」を養う(補腎)ための、今日からできるセルフケアです。
1. 食事:「黒い食材」+「生姜」
- 五行思想で「腎」の色は「黒」です。黒い食材は「腎」を補うとされています。
- (例)黒ゴマ、黒豆、ひじき、海苔、きくらげ、ごぼう、クルミ
- また、黒いもので言うと「イカ」も、墨が黒いので「腎」に該当すると考えることができます。私はいかめしがすごく好きで、この時期は積極的に摂るようにしています。
- 生姜(しょうが)
- これは直接「腎」を補うわけではありませんが、この季節は「生姜」を意識的にメニューに取り入れましょう。生姜は体の内部から私たちを温めてくれます。
2. 防寒:「腰」と「三首(さんくび)」を温める
- 特に温めてほしいのは「腰」(「腎」のツボが集中)と「三首」です。
- 「三首」とは、「首」「手首」「足首」のことです。東洋医学では、特に冬の間はこの三首を冷やさないように、と昔から伝えています。
3. 睡眠:「早寝遅起(はやねおそおき)」
- 冬は睡眠時間を意識的に少し延ばしたほうが良い、とされています。「早く寝て、遅く起きる」という意味です。
- 古代中国では太陽の日照時間と活動時間を比例させたので、日照時間が短くなる冬は、労働時間がおそらく短くなったのでしょう。(当時は電気がないので、夜間に火のない所での活動はリスクやコストパフォーマンスが悪かった、という背景もあると私は思っています。)
- 現代でこれをそのまま実行するのは難しいですが、「いつもより少し長く寝る」ことを意識してみてください。
【まとめ】(鍼灸院の役割)
こうしたセルフケアの中で、鍼灸治療とあわせて特におすすめしたいのは「お灸(きゅう)」です。
お灸は、私たち鍼灸師が院で行うだけでなく、ご自宅でできる「せんねん灸」のようなものもあります。 特定の「腎」のツボ(例えばおへその下にある「関元」や腰のツボなど)をお灸で補ってあげると、体が温まり、冬を格段に過ごしやすくなると思います。
ご自身の「腎」の状態が気になる方、慢性的な冷えや腰痛でお悩みの方は、ぜひ一度「横浜明堂鍼灸院」にご相談ください。