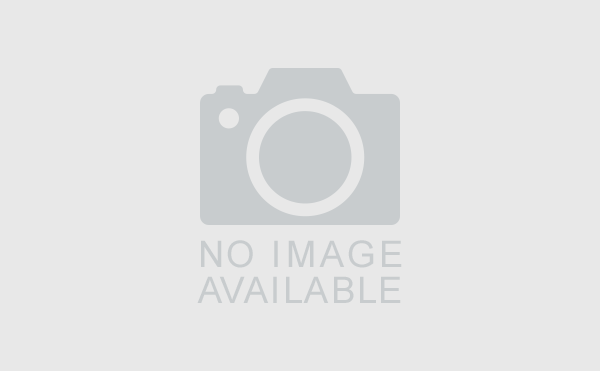こんにちは、横浜明堂鍼灸治療院の石尾です!
今週に入ってから冬の訪れを感じ、朝晩の空気がぐっと冷たくなってきましたね。 それに伴い、急な冷え込みで「首肩こり」が強くなってしまう患者さんが増えています。
こういった首肩こり、実は「冷え」が原因かもしれません。 東洋医学ではこれを「寒邪(かんじゃ)」と呼びます。
今日は東洋医学の知識でしっかり「寒邪」対策をして、一緒に健康に冬を乗り越えていきましょう。
なぜ寒くなると「こる」のか?
人間の体は、血流によって体の熱を保っています。 血流は筋肉や組織に充分な酸素や栄養を届けるだけでなく、体の熱を外に逃がしたり、逆に熱を逃がさないように調節する役割も担っています。
寒くなってくると、体は熱を逃がさないように自然と血管や筋肉を「キュッ」と固くさせます。 さらに、寒さから身を守ろうと「肩をすくめる」姿勢が、首や肩の筋肉を常に緊張させた状態にしてしまいます。
この緊張状態が通勤・通学の時間中ずっと続いていくと、自然と「首肩こり」になってしまうのです。
デスクワークの人は要注意
今、多くの方がデスクワークに携わっていますが、その姿勢はただでさえ首や肩に持続的な緊張を強いています。
その状態に「冷え」による緊張が加わるため、普段から首肩こりの人は、この時期さらに症状が悪化しやすいので注意が必要です。
寒邪(かんじゃ)とは?
東洋医学では、こういった「冷え」による不調全体のことを「寒邪(かんじゃ)」と呼びます。
「寒邪」は体の熱を奪い、「気・血(き・けつ)」のめぐりを滞らせる性質があります。
特に「寒邪」を考える上で注意したいのは「首の後ろ」です。 ここは「寒邪の玄関」とも呼ばれる場所で、ここが冷えると一気に不調が出やすくなるので注意しましょう。
対策1:3つの「首」を温める
このブログや当院のホームページで何度もお伝えしていますが、冷え対策で最も重要なのは「首」「手首」「足首」の3つの「首」です。
ここは皮膚のすぐ下に太い血管が通っているので、ここを効率的に温めるだけで、体温を非常に効率的に守ることができます。 「マフラー」「手袋」「レッグウォーマー」をぜひ活用してみましょう。
対策2:温活カイロのツボ
もしカイロを使うのであれば、おすすめの場所は「大椎(だいつい)」です。
「大椎」は、首を前に倒した時に一番出っ張る骨のすぐ下にあり、まさに「寒邪の玄関」を塞ぐ場所です。
(ちなみに私は、使い捨てではなく、充電式の電気カイロを冬は愛用しています。エコですし、温かさも調節できておすすめです)
同時にもう一つ、腰にある「腎兪(じんゆ)」というツボもおすすめです。腰(おへその真裏あたり)にカイロを貼ると、体全体のエネルギーが満ちてきますよ。
対策3:体を内側から温める食材
体を内側から温める食材もおすすめです。
- 生姜、ネギ、シナモン
- 大根、ニンジンなどの根菜類
こういった食材は、特にスープなどにして召し上がれば、体を芯から温めてくれるのでぜひ試してみてください。
最後に
昔の東洋の書物には「冬は働くな、冬眠しろ」と書いてあるほど、冬は体を休めるべき季節とされています。
本音を言えば、そうしたいものですよね(笑)。
しかし、なかなかそうもいかないのが現代社会です。 そういった時に皆さんに寄り添い、体の疲れをリセットするのが鍼灸治療です。
「セルフケアでも追いつかない…」 「芯から冷え切っている気がする…」
そんな時は、どうぞ当院の鍼灸治療をご活用ください。