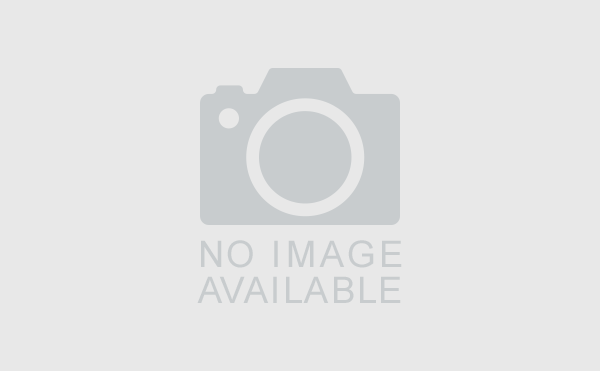お灸と鍼の違い
こんにちは横浜明堂鍼灸院の石尾です
患者様から治療についてご説明する際、 「鍼(はり)と灸(きゅう)って、何が違うんですか?」 「どちらもツボを刺激するのは同じですよね?」 というご質問をよくいただきます。
その通り、どちらも「ツボを刺激して体の不調を整える」という点では同じです。
しかし、実は「刺激の質」が違います。 そして、それに合わせて「治療の目的」も少しずつ異なってくるのです。
今回は、この「鍼」と「灸」の違いと、当院での使い分けについて解説します。
鍼灸のキホン:「補う」か「取り除く」か
少し専門的な話になりますが、東洋医学には「補瀉(ほしゃ)」という大切な概念があります。
- 補(ほ):足りないもの(元気、血流など)を「補う」こと
- 瀉(しゃ):余分なもの(邪気、痛み、熱など)を「取り除く」こと
体調不良は、この「足りない」か「余分にある」かのバランスが崩れた状態と考えます。
「鍼(はり)」は、この「補瀉」の使い分けが非常に得意な治療法です。 一方、「灸(きゅう)」でこの補瀉を細かく使い分けるのは、少し技術的に難しくなります(もちろん、お上手な先生は使い分けられます)。
この基本的な違いを踏まえて、当院での使い分けをご紹介します。
当院における「鍼(はり)」の役割
当院の鍼治療は、東洋医学的な側面だけでなく、解剖学や生理学といった西洋医学的な知識も組み合わせて行います。
1. 東洋医学的な使い方(体質改善)
前述の「補瀉」を使い分け、体全体のバランスを整え、不調の根本原因にアプローチします。
2. 西洋医学的な使い方(筋肉への直接アプローチ)
「ガチガチの肩こり」「つらい腰痛」「寝違えで首が回らない」といった場合、硬くなった筋肉(トリガーポイント)に直接アプローチします。 例えば、寝違えの際には脇の下の筋肉に鍼をすることもあります。
このように、鍼は「体質改善(補瀉)」と「筋肉への直接アプローチ」の両方の観点で使うことができる、非常に汎用性の高いツールです。
当院における「灸(きゅう)」の役割
一方、当院で「灸(きゅう)」を使う際は、主に「温熱療法」として用いる場面が非常に多いです。
その最大の目的は、熱を加えて「冷え」を取り除くこと。
特に冬場に多いのですが、 「この頭痛、冷えから来ていますね」 「腰痛の原因は、下半身の冷えですね」 といったケースは意外なほど多くあります。
そういった**「冷え」を取り除いてあげるだけで、あっさり解決する頭痛、腰痛、肩こり**も少なくありません。 そんな時に使いやすいのが「灸」です。
単純な比較ですが、男女で比べると、当院では女性にお灸を使う率がとても高いです。それだけ「冷え」に悩んでおられる方が多いのだと思います。
また、ご自宅で「せんねん灸」などを使ってセルフケアができる点も、鍼にはない「灸」の大きな利点の一つですね。
まとめ
当院では、それぞれの得意分野を活かして鍼と灸を使い分けています。
- 鍼(はり):体質改善(補瀉)と、筋肉への直接アプローチ
- 灸(きゅう):温熱療法(冷えの除去)
「お灸は試したことがない」「なんだか熱そう…」という方も多いのですが、賢く使えば体の不調を整える素晴らしい効果が期待できます。
冷えが気になる方、鍼治療だけでは取りきれない不調がある方は、ぜひ一度ご相談ください。