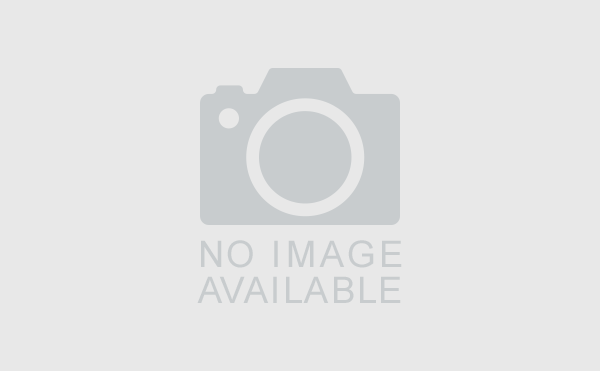なぜ温活しても冷える? 薬膳の視点から解説する正しい温活法
こんにちは、横浜明堂鍼灸院の石尾です。
「温活」という言葉を最近よく聞くようになりましたが、皆さんはどのような温活を実践されていますか?
今週末からは二十四節気の「小雪(しょうせつ)」に入り、これから寒さが本格的に厳しくなってきます。体を温めることは、免疫力を高め、流行しているインフルエンザなどにも負けない体を作る上で非常に重要です。
今日は、鍼灸師であり、薬膳的な観点も重視する私がオススメする、失敗しない温活の仕方をご紹介したいと思います。
習慣①:【食】薬膳の視点を取り入れる
体を内側から温める「食」の習慣から見直しましょう。
- 体を温める「陽」の食材を摂る 薬膳の基本的な考え方は、鍼灸と同じく「陰陽」です。体を温める**「陽(よう)」のエネルギー**を持つ根菜類(ごぼう、にんじん、大根など)を中心に食べてみましょう。こういった食材でスープを作るのもとても良いですね。
- 生姜は最強の薬味 体を温める食べ物として有名な生姜ですが、加熱したときに発生する「ショウガオール」は、より強い発熱作用を持つと言われています。積極的に料理に取り入れましょう。
- 体調が優れないときは 風邪の引き始めなど、少し体調が悪い日が続いたり、寒気が激しいというときには、漢方の「葛根湯」を早めに飲んであげるというのも有効です。(※ご自身の体質に合わせてご判断ください)
習慣②:【動】ふくらはぎを動かす「第二の心臓」温活
激しい運動である必要はありません。体を動かさなくなってしまうと、熱を生み出す力も、血液を巡らせる力も落ちてしまいます。
- 朝の「動」で一日をスタート 朝日を浴びるための5分から10分程度の軽い散歩やストレッチがおすすめです。
- 「ふくらはぎ」を意識する ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、全身の血液を心臓に戻すために重要な役割を担っています。朝からふくらはぎを動かすことで、その日一日すっきりと、血流の良い状態で過ごせるようになります。
習慣③:【習慣】冷たいものを避け、体を芯から温める
冷えは、外側よりも内側からくる影響が大きい、というのが東洋医学の根幹的な考え方です。
- 冷たい飲み物は厳禁 内側から温めることがとても大事になりますが、冷たいもの、特に氷が入っているものを飲んでしまうと、自分の中から体温を奪い、胃腸の働きを悪くしてしまいます。なるべく常温以上の飲み物を選びましょう。
- シャワーよりも「ぬるめのお風呂」 暑いお風呂に入る必要はなく、むしろぬるめのお風呂にゆったりと入ることで、皮膚表面だけでなく、体の芯まで熱が入ってくれます。シャワーで済ませず、湯船に浸かる習慣をつけましょう。
東洋医学の視点:冷えは「体の信号」
最後に、東洋医学では「冷えは万病の元」「究極の冷えは死である」という考え方があります。これは大昔の中国で、冷たくなった体を「死」と捉えていたことに由来します。
とにかく、体が「冷えている」状態を避けることが、健康の基本なんですね。
「暑い夏を迎えた年の冬は、厳しい冬が待っている」とも言われます。今年の夏は特に暑かったので、もしかしたら今年の冬は例年以上に冷え込みが激しいかもしれません。
セルフケアで温活をしつつも、溜まりきった冷えは鍼灸の力でしっかり取り除き、この冬も健やかに乗り切ってきましょう!